「これが世界最高峰のレースなのか・・・。」
2025年F1第8戦、伝統のモナコGPを観戦しながら、思わずつぶやいてしまった。
ここはモナコ モンテカルロ、絶対に抜けない!
2025年に生じた問題に触れる前に、前提に触れておきたいと思う。
それはモナコGPの舞台となるモンテカルロ市街地コースが、他に類を見ないほど「オーバーテイクが難しいコース」だということ。
これを象徴するエピソードはいくつかあるが、特に有名なのは1992年のナイジェル・マンセル対アイルトン・セナの名勝負だろう。
このレースはマンセルがトップを独走していたが、残り数周でタイヤトラブルによりピットイン。
これによってセナがトップに躍り出るが、マンセルはセナより2秒近くも速いラップですぐに背後に追いついてしまう。
しかし抜けない。
フジテレビの三宅アナが発した「ここはモナコ モンテカルロ、絶対に抜けない!」という名言は、日本の古くからのF1ファンなら誰もが知っているだろう。
また近年では2019年、ボロボロのタイヤでマックス・フェルスタッペンの猛追を20周にも渡り防ぎ切ったルイス・ハミルトンの走りも見ごたえがあった。
ヌーベル・シケインでは軽い接触もあったし、1992年よりも強く印象に残っている人も多いかもしれない。
とにかくモンテカルロは抜きにくいコースなのだ。
そのうえF1マシンは時代を追うごとにサイズが大きくなっており、これもまた抜きにくさに拍車をかけている。
そしてついにレースのパレード化が深刻化したのが2024年。
この年は予選トップ10の順位が決勝レース終了まで一切変動しないという、F1史上初の珍事が発生した。
レース開始直後、セルジオ・ペレスとケビン・マグヌッセンが接触し、ニコ・ヒュルケンベルグも巻き込まれる多重クラッシュが発生。
これにより赤旗が提示されてレースが中断すると、各チームはこの間にタイヤ交換義務を消化。
このため再スタート後は追加のピットストップが不要となり、戦略的な差異が生まれる余地がなくなった。
そのうえ、ドライバーたちはタイヤを温存するために極端なタイヤマネジメントを実施。
2位に終わったオスカー・ピアストリが「F2よりも遅いペースだった」と述べるほどで、このような状況ではオーバーテイクはより難しくなり、余計に順位変動が起こりにくくなってしまった。
こういった事態の再来を防ぐため、2025年のモナコGPでは、全ドライバーに最低2回のピットストップとタイヤ交換を義務付ける新ルールが導入された。
コース上で順位変動が起きないのであれば、戦略的な順位変動によってレースを活性化させようという魂胆だ。
これによって、2025年のモナコGPでは確かに様々な動きを見ることができた。
しかし、これが成功だと感じた人はそれほど多くないだろう。
その理由によって、私は冒頭のようなつぶやきをするに至る。
画面に向かって、一人で。かなしい。
レーシングブルズの奇策
先述の通り、2025年のモナコGPでは、全ドライバーに最低2回のピットストップとタイヤ交換を義務付ける新ルールが導入された。
これに対し、レース前は「スタート直後に1回目のタイヤ交換を済ませるチームがいるだろう」とか、「セーフティーカーが出たらその間に一気に2回ピットインするマシンもいるかもしれない」とか、様々な予想がみられた。
しかし現実はさらに上をいった。まるでSF小説でも読んでいるかのような意外性。
レーシングブルズのリアム・ローソンが、チームメイトのイザック・アジャに2回のフリーストップ(順位が下がらないピットストップ)を提供するために、後続を抑えながら極端にペースを落とし始めたのだ。
ローソンが後続を抑える間に20秒以上のリードを築いたアジャは、1度目のピットストップとソフトタイヤへの変更を済ませて、ローソンの前に復帰。
そのままペースを上げ、わずか5周後には再度フリーストップ。あっという間にすべての義務を消化してしまった。
さらに後続のウイリアムズやメルセデスも同じ戦略を取り、抑えられる後続はどんどんレース権を失っていく。
見方によっては、これは確かにルールに則った素晴らしい戦略だった。
ウイリアムズが戦略を真似たこともあって、レーシングブルズは2台そろって貴重なポイントを獲得。
まさにこれ以上ない結果を得たと言ってもいい。
レーシングブルズやウイリアムズを応援する人にとっては最高の週末になったかもしれない。
しかし、これは果たして本当にレースだったのか。
しかも走っているのは世界最高峰を誇るF1マシンである。
ローソンが後続を抑えているとき、ラップタイムは1分20秒を下回っていた。
ファステストラップはランド・ノリスが最終ラップにたたき出した1:13.221、
当のローソンですら、自身のファステストラップは1:15.321だ。
誰かが意図的にスロー走行をする間、後続はただパレードの一員となることを受け入れるしかない。
特に、ここはモナコ、モンテカルロなのだから。
クラッシュゲートと何が違う?
このレース、トップ4台の争いはある程度の見ごたえがあり、「レース」をしていたと評価する声も多い。
しかし、実はトップ争いにも大きなギャンブル要素がみられた。
51周目、ランド・ノリスが2度目のピットインをすると、トップに躍り出たマックス・フェルスタッペンは、最後のピットストップを残したまま、全78周中77周目までコース上に留まり続けたのだ。
彼とレッドブルが狙ったのはたった一つの勝利の可能性、赤旗によるレース中断だった。
赤旗によってレースが中断すると、各マシンはピットに戻り、そこではタイヤ交換が認められる。
もし赤旗が出れば、フェルスタッペンは順位を落とさずに2度目の義務を消化できる。
これもまた抜けないモナコならではのギャンブルだった。
ここで一つの可能性に気付く。
「クラッシュゲート」だ。
過去、F1においては「クラッシュゲート」と呼ばれる疑惑が度々あった。
意味合いとしては「故意のクラッシュ疑惑(事件)」みたいなニュアンス。
この言葉自体が使われるようになったのは、2008年のシンガポールGPの事件以降だと記憶している。
ネルソン・ピケJr.のクラッシュによりセーフティーカーが出動。
そのタイミングの絶妙さによって、チームメイトのフェルナンド・アロンソは、後方スタートながら見事優勝することに成功した。
翌年になって、このクラッシュが「チームの指示による意図的なもの」であったことが判明し、大変大きな問題となった。
今回のレース、51周目以降にフェルスタッペンのチームメイトの角田裕毅がクラッシュをして赤旗を出せば、フェルスタッペンは優勝することができた。
もちろんこれは先のクラッシュゲートと同じくまったく許されることではないし、当然レッドブルも角田もその選択はしなかった。
彼らの名誉のために言うが、これはあくまで可能性の話であって、実際は議論すらされていないだろう。
だが、今回レーシングブルズやウイリアムズ、メルセデスが取ったスロー走行によるフリーピットストップ戦法と、この可能性としてあり得たクラッシューゲートは何が違うのか。
なぜ後者がダメで前者はオーケーなのか、納得できる説明ができる人はどのくらいいるだろうか。
少なくとも私にはできない。
「危険性の有無だ」と言う人もいるだろうが、これについては「極端なスロー走行も危険性をはらむ」という反論が可能だ。
でなければ予選の107%ルールの存在意義がなくなる。
私が思う唯一の違いは、あらかじめルールで禁止されているか否か。
さらに付け加えるなら、それがこっそり行われたか、堂々と行われたかということも大きな違いかもしれない。なんていう皮肉だ。
「想定されていなかったのではないか」という意見もあるが、しかし過去にも似たような例はあった。
例えば2024年のサウジアラビアGP、ハースのケビン・マグヌッセンが後続をブロックし、チームメイトのニコ・ヒュルケンベルグは10位に入りポイントを獲得。
この前段階として、アレックス・アルボンとの接触や角田裕毅をコース外で追い越すなどの行為があり、2つの10秒ペナルティを受けたことも話題となった。
2024年にはもう一つ似た事例があった。
モナコGPだ。
当時レーシングブルズの角田は、今回のローソンと同じく、1分20秒台までペースを落としながらアレックス・アルボンを抑えて走った。
先述の通り、2024年のモナコGPは全車が1周目にタイヤ交換義務を済ませ、我慢のレース展開となっていた。
もし角田がペースを上げ、アルボンと後続のピエール・ガスリーとの間に大きなギャップが生まれたら、アルボンはフリーストップが可能となり、新品のタイヤでやすやすと角田に追いつき、わずかながら追い抜く可能性も増していただろう。
しかし角田は完全にペースをコントロールし、後続のタイヤ交換を防ぐことに成功した。
レース最終盤、チームの許可を得た角田は1分14秒台でラップしており、いかにペースをコントロールしていたかを知らしめることとなった。
2021年最終戦のアブダビGPでペレスがハミルトンをブロックした伝説の走りは・・・あれは意図的にペースを落としたわけではないのでまた別の話か。
とにかく、他車を巻き込む意図的なペースダウンは過去にもあり、ルールはそれを容認し続けている。
通常、前走車に大きなリードを築かせるほど、自車のペースを落としながら後続をブロックし続けるのは、そう簡単なことではない。
だからこそ、ルールで禁止する必要性はないと判断されたのか、あるいは多少はあった方がレースが活性化するという見方もあるのか。
個人的には決勝にも107%ルールに似たルールを設けてはどうかと思うが、これもフラッシュアイデアの一つに過ぎない。
「こんなレースは間違っている」
これは自身も今回の低速走法作戦を採用したウイリアムズのジェームス・ボウルズ代表の言葉だ。
彼は、パフォーマンスと持っている武器でレースをしたいが、モナコのルールとレギュレーションがまだその域に達していないといった内容の発言をし、改善を求めた。
唯一、レース中盤、ジョージ・ラッセルがペナルティ覚悟でシケインをカットしてウイリアムズを追い抜いて行ったのは爽快だった。
ルール上はラッセルの行いが違反であることに議論の余地はないが、つまらない戦略を強引に打ち破りに行く姿勢に、異魔神を喰らう竜王のような力強さを感じた。
え、わかりにくい?
例えるならチェス盤を丸ごとひっくり返すような、あるいはピッキングで鍵を開けようとしてる横でドアを蹴破るような、そんな強引さ。
そのあとメルセデスが同じ戦略を取ったのにはがっかりしたが、こればかりは仕方ない。
ラッセルはF1レーサーだったし、チームは最大の結果を得るために他に選択肢がなかった。
問題はルールとレギュレーションだ。
来年もまた似たようなことが起きれば、伝統のモナコGPがカレンダーから消える日もそう遠くなくなるだろう。
世界最高峰の”レース”が観たい。
今後どのような改善がみられるか。
LET’S WAIT AND SEE.
それからノリス、優勝おめでとう!
まだシーズン1/3が終わったばかり。まだまだわからないぞ!
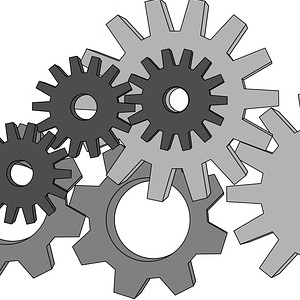
コメント